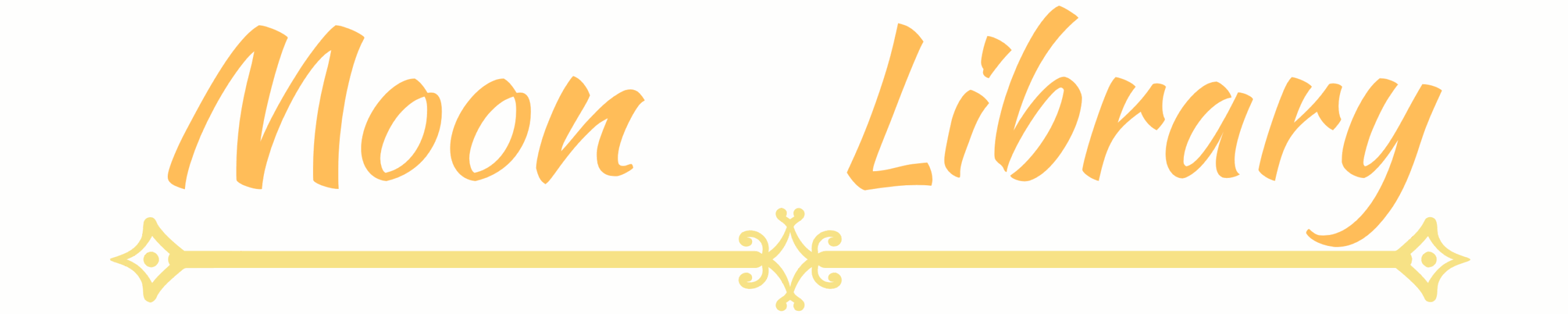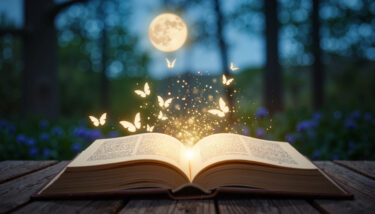今日もお疲れさまでした。
あなたは自分の好きなことをして生きていますか?
忙しい日々でも、自分の人生を生きることは大切です。
なぜ、わたしは自分の人生を生きているところを、あの子たちに見せてやらなかったのか
伊予原新(2021).『月まで三キロ』株式会社新潮社
『月まで三キロ』の一遍 山を刻む に登場する言葉です。
自分の好きなことをしないまま生きると後悔するかもしれないことを教えてくれます。
<言葉についてのあらすじ>
主人公は50代の女性。
主人公は今まで母親として、家族が求めるまま、ただそれに応え続けてきた。
家族は皆好き勝手し、誰にも感謝されず、心身を気遣われることもない。
夫は家のことに無関心で、義母にはいつも嫌味を言われる。
息子は「まともに働くヤツはバカだ」と定職に就かない。
娘は「お母さんみたいにはなりたくない」と言い、家を出ていった。
主人公が山に高山植物の撮影に来ていると、火山学者の先生と学生に出会う。
先生は火山研究が楽しそうで、この人はなりたいものになった人だと主人公は思った。
娘にとって一番『なりたくない』ものになっていた自分とは正反対だった。
でも主人公にも山岳写真家という夢があり、山の写真をコンクールに投稿していたこともあった。
結婚・出産と忙しくなったことで夢は消えてしまったが、山が大好きだったのだ。
同行していた学生は、先生の好きなことを仕事にする生き方を見て、自分もあの先生と研究を続けたいと、嬉しそうに話す。
彼は好きなことを突き詰める先生の生き方に感染したいのだと主人公には理解できた。
先生と、親としての自分を比べて肩を落とす。
下山の時、心地よい風が吹き、先生が学生に言う。
「山って、いいだろ」
それを聞いて主人公の足が止まる。
わたしはそのセリフを子どもたちの前で一度も言ったことがない。
あんなに山が好きだったのに、山に連れてきてもないし、山の魅力を語ったこともない。
主人公は今までを振り返り、自分の失敗を痛感する。
なぜわたしは自分の人生を生きているところを、あの子たちに見せてやらなかったのか。
<まとめ>
自分の好きなことを追及して、自分の人生を生きる人は魅力的です。
人を引きつける力も、周りに元気を与える力もあります。
反対に好きなことをせず、周りに合わせてただ日々のTo Doに追われて生きる人には、誰も魅力を感じないでしょう。
この主人公は母親として家族を支えるために、様々なことに耐え、本当に頑張ってきました。
でも彼女は自分の好きなこと忘れ、ただただ周囲に振り回されていました。
そんな自分がない、自分の人生を生きていない母親を見て、子どもたちは思ってしまったのです。
「こうはなりたくない」
主人公は誰もわたしに感謝や気遣いをしないと、自分を被害者のように語っています。
でもそうなった原因は、このような生き方をしていた主人公にもあったのかもしれません。
自分の好き・楽しいは才能であり財産です。
後悔しないように、自分の人生を生きましょう。
『月まで三キロ』は科学の世界と人間のドラマを上手く融合させた6つの短編からなる小説です。
月や雪結晶、粒子といった科学的な事象を人同士の関係性や境遇、人の生き方に落とし込んだとても面白い作品でした。
気になった人はぜひ読んでみてください。
参考
伊予原新(2021).『月まで三キロ』株式会社新潮社
Testosterone(2021).『読むだけで元気が出る100の言葉』きずな出版